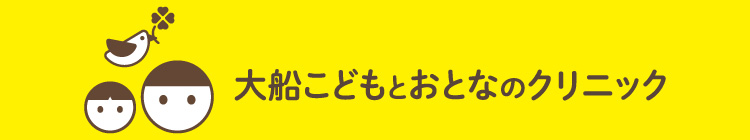専門外来 - こどもの発達こころの外来 毎週水曜日
診察時間 午前9時~午後13時 午後14時~18時30分
お一人1回 15分となります。(お時間を過ぎた場合は、次回の予約をお取りします。)
診療内容神経発達症(自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害)、起立性調節障害、睡眠障害、チック、心のお悩み相談
対象年齢高校3年生まで(18歳になられた方は、窓口・TEL予約となります)
注意事項
・60日前から10日前まで予約をお取りいただけます。
※キャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。
・初回の方は予約時間の10分前、再診の方は5分前までに受付をお済ませください。
・web問診を入力しないまま来院された場合や、遅れて来院された場合は後の患者様にご迷惑がかかるため、診察時間が削られます。渋滞、電車遅延など考慮いたしかねますので、時間に余裕を持ってお越しください。
・予約当日の時間変更や日程変更は困難となります。
・起立試験は「金曜日の午前」のみ実施しております。
予約方法
・ネット予約、電話予約、窓口予約
・60日前から10日前まで予約をお取りいただけます。
・水曜日の専門外来を初めて受診される方は、必ず「水曜日(初回)」の予約枠でご予約をお取りください。
問診票の入力
・事前にweb問診の入力をお願いします。
(初回の方:予約日の10日前までに 再診の方:予約日の前日までに)
・当院に初めて受診される方は、初診の方用の問診票の記入を併せてお願いしています。
ご来院前にプリントアウトしてご記入いただくと、当日のお手間が省けます。
・曜日を変更して専門外来を受診される場合、改めて問診・相談からのスタートとなりますので、新たな曜日の初回用問診票の入力をお願いいたします。
WEB予約・問診票の入力はこちら
受診の際、お持ちいただくもの
保険証・医療証・母子手帳・おくすり手帳・紹介状(お持ちの方)・動画(症状が出現した際の動画・写真・メモ等)
診療内容詳細(クリックまたはタップで開きます。)
1神経発達症(発達障害)
<自閉症スペクトラム障害(ASD)>
ASD(自閉スペクトラム症)は、「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られる発達障害の一つです。
自閉スペクトラム症を含む、小児の精神神経疾患には、それぞれのお子さんに適した診察・指導や関わり方が必要です。
お子さんの発達に関して、ご心配やご不安のある方はご相談ください。
※症状に応じて、発達検査、自閉症スペクトラム障害、ADHD、小児うつなどの検査、診断を行います。
周囲からの支援や配慮を得やすくするための各種診断書・意見書についての記載にも相談にのらせて頂きます。
<注意欠陥多動性障害(ADHD)>
ADHDは、注意欠如多動症とも呼ばれ、話を集中して聞けない、作業が不正確で、なくしものが多いなどの「不注意」、体を絶えず動かす、座ったままいられない、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性がみられる発達障害の一つです。
ADHDの子どもは、このような特性により家庭や保育園・幼稚園、学校などの環境と合わず、「授業中に立ち歩いてしまう」「忘れ物・なくしものが多い」「友達とうまく関係が築けない」などの困り事が多くあります。
お子さんの発達に関して、ご心配やご不安のある方はご相談ください。
※症状に応じて、発達検査、自閉症スペクトラム障害、ADHD、小児うつなどの検査、診断を行います。
周囲からの支援や配慮を得やすくするための各種診断書・意見書についての記載にも相談にのらせて頂きます。
2起立性調節障害
朝になかなか起きることが出来ない、朝の食欲不振、全身倦怠感、頭痛、立っていると気分が悪くなる、立ちくらみなどの症状が起こります。
症状は午前中に強く、午後からは体調が回復することが多いです。夜には元気になり、逆に目がさえて眠れないこともあります。
「どこに相談したらよいか分からない」という方も多いようです。
そのような方は当クリニックの専門医師に一度相談にいただくと見通しが立つと思います。
※起立試験は金曜日の午前のみ実施しております。
曜日を変更して専門外来を受診される場合、改めて問診・相談からのスタートとなりますので、新たな曜日の初回用問診票の入力をお願いいたします。
3睡眠障害
子どもの不眠症としては、生後6か月以降の夜泣き、2歳以降の寝ぐずり(行動性不眠症)、不適切な環境・ストレスによる不眠症、発達障害に合併する不眠症などがあります。
放置すると生活習慣病や対人関係の問題、学習障害、危険行動の増加など多岐に渡って悪影響を及ぼす可能性があります。まずは一度、当院の専門医師に相談してみませんか。
4チック
子どもが目をぱちぱちさせる、鼻をひくひくさせる、顔をしかめたり、肩をすくめたりすることはありませんか?
風邪でもないのに咳払いをする、「アッ」とか「オッ」と声を出す、鼻をクンクン鳴らす、わいせつな言葉など「社会的に容認し難い言葉」を言ってはいけないと分かっているのに言ってしまう(汚言症)などがあります。
一度、当院の専門医師に相談してみませんか。